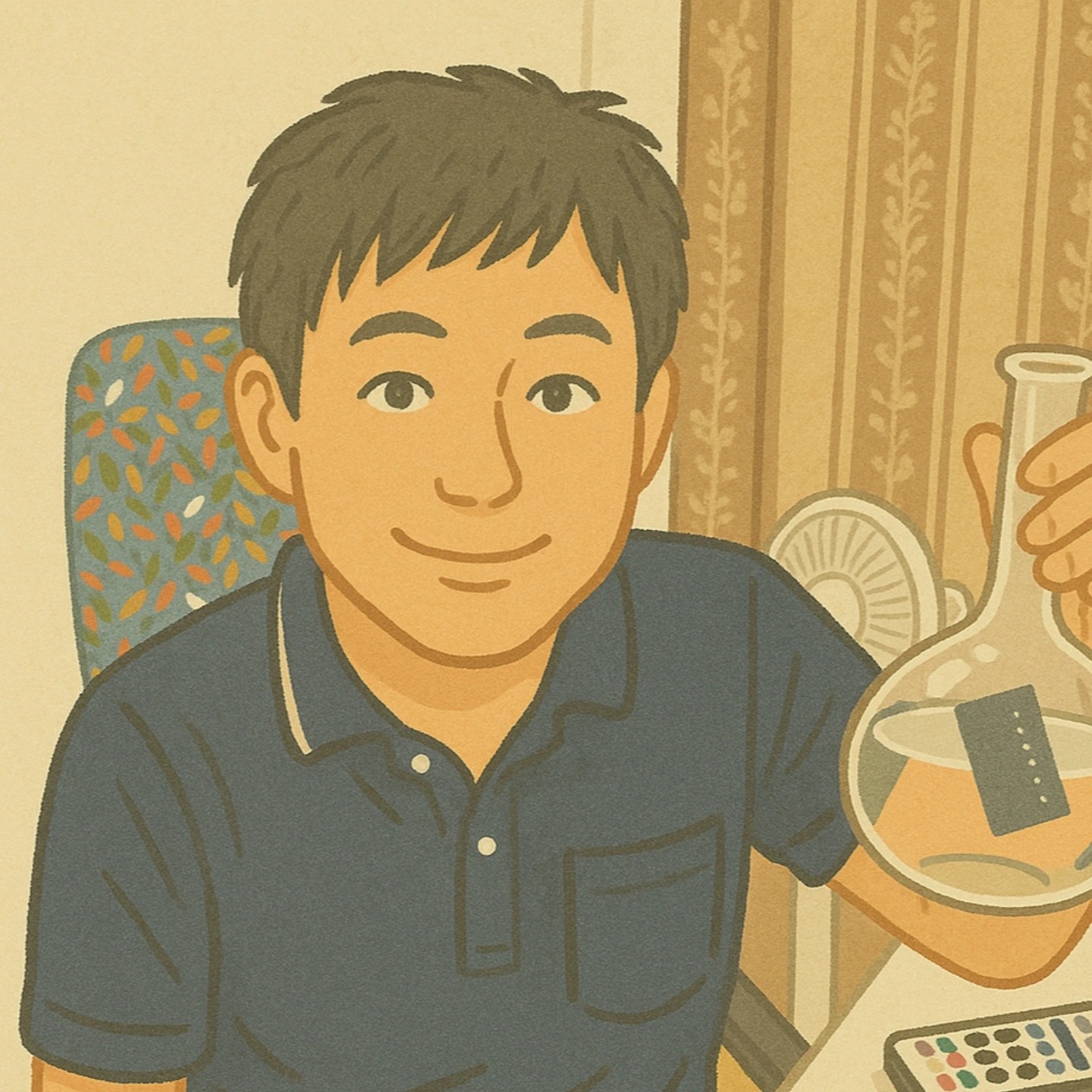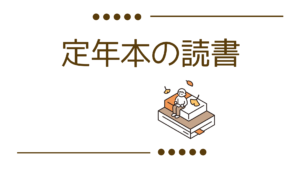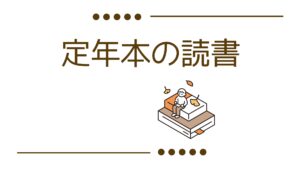この本で、筆者は、定年を迎える60歳から投資を始めるのは遅いということは決してないと述べています。定年後に30~40年と投資・運用できる時間があるならば、元本割れせずお金を増やせる可能性も、増やしつつお金を使うことで「資産寿命」を延ばせる可能性も非常に高くなるということです。本書では、60歳からの資産形成の話とともに、自分の寿命に向けて、心の安定も得ながら、資産をうまく使いきっていく実践方法が解説されています。
筆者の頼藤太希さんは、(株)Money&You代表取締役をされているマネーコンサルタントです。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生命保険会社にて資産運用リスク管理業務に従事し、2015年に創業し、現在に至っております。また、女性向けWebメディア「FP Café」や、動画チャンネル「Money&YouTV」を運営されています。その著書には、「定年後ずっと困らないお金の話」(だいわ文庫)、「はじめてのNISA&iDeCo」(成美堂出版)、「11歳から親子で考えるお金の教科書」(日経BP)、「定年前後 一番トクするお金の話」(パワームック)など多数あります。
この本は、次の6章で構成されています。
- 第1章 60歳から投資をしないほうがリスキーな時代
- 第2章 安心の老後生活に向けた、60歳からのコア・サテライト戦略
- 第3章 資産寿命を延ばしながら上手に使い切る!?賢い出口戦略
- 第4章 60歳からの投資で検討したい金融商品
- 第5章 60歳からの資産取り崩し“運用モデル・シミュレーション”
- 終章 必ず来る相場暴落の時、どうする?
この本の前半で、筆者は、「60歳から投資をしないほうがリスキーな時代」について書いています。印象に残ったのは次のような点です。
- 物価が上昇しても、年金受給額はそれほど増えない。これは、将来の年金給付を維持するための「マクロ経済スライド」という仕組みによって、増加率が抑えられるからである。
- 年金の受給開始は原則65歳だが、繰り下げ受給により、1か月遅らせるごとに0.7%、75歳まで10年間繰り下げることで最大84%も増やすことができる。
- 定年後の働き方には再雇用、再就職、フリーランス、企業などがあるが、どれを選んでも定年前より収入は下がる。しかし、働くことで、収入が得られるのはもちろん、社会との繋がりも持てるし、健康維持にもメリットがある。
- 年金収入が定年後を支えるメインの収入、勤労収入が老後前半を支える収入、資産運用収入が老後後半を支える収入である。これらが定年後の収入源の基本の3本柱となる。
- 物価上昇率が高くなればなるほど、現金の価値は減っていく。物価上昇率2%が3年続いたら、1000万円の価値は、545万円になってしまう。
- 新NISAのメリットは、①一生涯にわたって運用益が非課税になる、②つみたて投資枠の商品が絞り込まれていて選びやすい、③成長投資枠で自由度の高い投資ができる、④非課税の投資が手間なくできる、⑤資産をいつでも引き出して使えることである。
- 新NISAは万能な制度ではなく、元本割れの可能性を低くするには、少なくとも15年から20年以上継続して運用を行う必要がある。老後資金のように10年以上使わない将来のためのお金を貯めたり、運用しながら取り崩したりするには最適の制度である。
- 就職してから退職までは「資産形成期」で、退職後は「資産取り崩し期」に入るが、退職日に全額資産を売却して預貯金に切り替えて取り崩すことはすすめられない。資産運用しながら取り崩すことで、資産寿命を延ばせるからである。
この本の中盤で、筆者は、「安心の老後生活に向けた、60歳からのコア・サテライト戦略」「資産寿命を延ばしながら上手に使い切る!?賢い出口戦略」について書いています。印象に残ったのは次のような点です。
- 資産の7割以上はリスクを抑える守りの「コア資産」とし、リターンを狙いに行く攻めの「サテライト資産」を3割以下の配分とすることで、お金を減らさずに増やす運用を目指すのが「コア・サテライト戦略」である。
- 個人の投資でも、コア・サテライト戦略は活用できる。コア資産では比較的リスクの低い資産を利用して安定成長を目指し、サテライト資産では個別株やアクティブファンドなど、リスクの高い資産を利用して利益の積み増しを狙う。
- 値動きと上手に付き合って堅実にお金を増やすのが、長期投資・積立投資・分散投資の「投資の3原則」である。特にコア資産は、この3原則を徹底したい。
- 60歳までに預貯金300~500万円とは別に、500万円の投資資金を作ることを目標にする。60歳以降は、その投資資金を投資に回しつつ、70歳までの勤労収入の一部(月1~5万円程度)の積立投資を10年間続けて行うのが基本戦略である。
- 資産の取り崩し期(70歳前後)に入ったら、預貯金300~500万円、キャッシュフローを生む資産300~500万円を確保したうえで、残りの資産を取り崩すことを考える。預貯金は、病気や介護に備えるお金として生涯保有を続ける。
- 資産の取り崩し時期は、リスクの高い資産から現金化して取り崩していく。年齢が上がると、市場が大きく下落した場合、回復するまで待つのが難しいケースがあり、また、資産売却の判断力が衰えるリスクもあるからである。
- 定額取り崩しと定率取り崩しのデメリットを補完する方法としておすすめなのが、資産が多いうちは定率取り崩し、少なくなったら定額取り崩しに切り替える「前半定率・後半定額」戦略である。
この本の後半で、筆者は、「60歳からの投資で検討したい金融商品」「60歳からの資産取り崩し“運用モデル・シミュレーション”」「必ず来る相場暴落の時、どうする?」について書いています。印象に残ったのは次のような点です。
- 70歳までは運用益非課税の恩恵が受けられる新NISAを最大限活用して、複利効果が得られる投資先に投資する。投資はなるべくシンプルを心がけて、分かりやすい商品で長期・積立・分散投資を行うようにする。
- 70歳以降は、資産の一部をキャッシュフローを生む資産に切り替えていく。配分金や分配金が非課税で受け取れるから、なるべく新NISAを活用した方がいいことは言うまでもない。
- キャッシュフローを生む資産は、持ち続けることで定期的に収入を得ることができるため、生涯にわたってずっと売らずに保有することが一つの手である。収入減をカバーできるし、心理的な不安も減らすことができる。
- 投資信託はアクティブ型よりインデックス型の方が実際の投資成績が良いケースが多くある。また、アクティブ型の場合、コストである信託報酬が高いので、利益を伸ばしにくい現実がある。
- 総じて高配当株よりも連続増配株のほうが株価上昇も含めたトータルリターンは高い傾向にある。市場全体の暴落にも強いのが特徴である。
- 配当利回りが高いからといってすぐに飛びつくのはやめるべきである。配当利回りが高い銘柄の中には、株価が下がって配当利回りが高くなっているような不人気銘柄が入っている可能性もあるからである。
- 投資の格言に「上げ100日、下げ3日」というものがある。市場の値上がりは緩やかだが、値下がりはわずかな期間で起こることを言い表したものである。
- 暴落があった時にもっともやってはいけないことは、慌てて売ることである。暴落に慌てて売ってしまうと、値下がりしたタイミングで利益(または損失)が確定してしまう。そのうえ、その後の値上がりによる資産回復の恩恵も受けられなくなる。
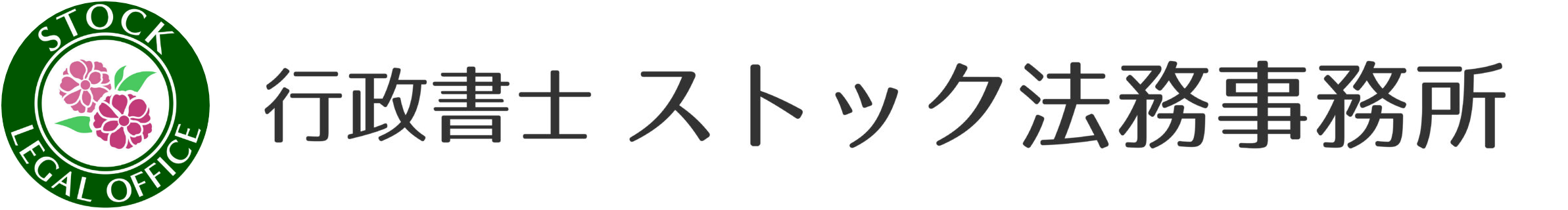
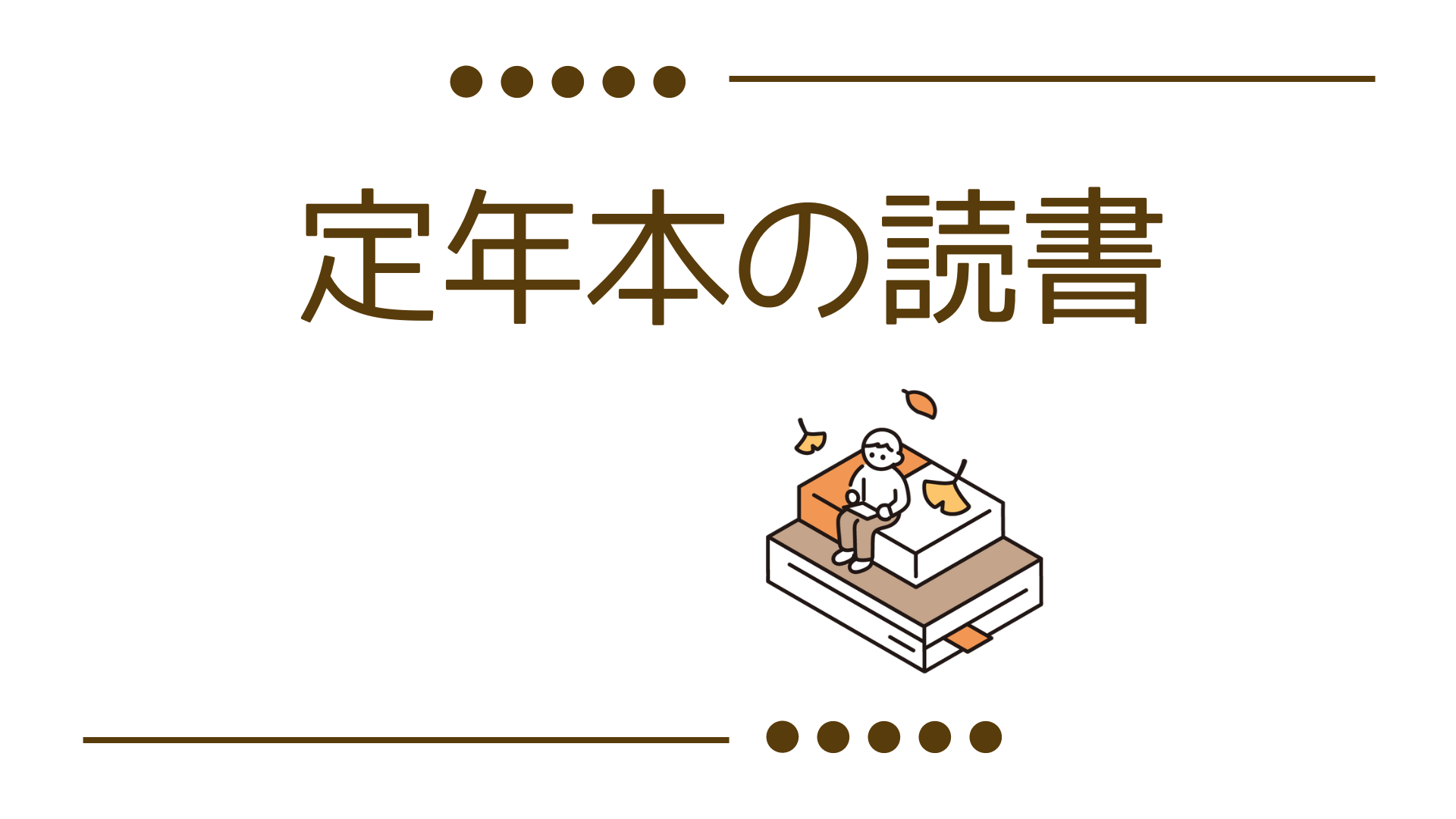
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/37c4e8aa.5274bab0.37c4e8ac.6b90fe35/?me_id=1213310&item_id=21265737&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6978%2F9784413046978_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)