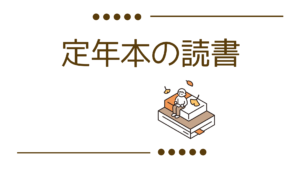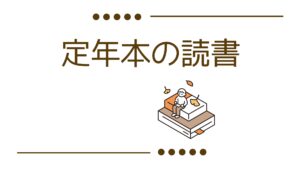この本は、大学医学部の教職員を長く勤め定年退職した筆者が、定年後10年を振り返って書かれたものです。筆者は、あらためて定年後の過ごし方について、それまでの自身の体験を基に定年後の生き方、そして、老いのとのつきあい方を総括したということです。これから定年後を迎える人の身支度に、また、定年後の人には生活の軌道修正をするうえでの参考になればとの思いで書かれたというものです。
筆者の石川恭三さんは、慶應義塾大学医学部卒業後、杏林大学医学部教授、大学付属病院副院長などを歴任され、2001年3月に定年退職された循環器・心臓病の分野を専門とする医師です。不整脈・心臓病の名医と言われています。著書に「定年ちょっといい話 閑中忙あり」(集英社文庫)、「医者が見つめた老いを生きるということ」(集英社文庫)、「健康ちょっといい話」(集英社文庫)、「老いのトリセツ」(河出書房新社)など多数あります。
この本は、次の3部で構成されています。
- 第1部 定年後を心豊かに生きる身支度 定年後で失うもの 手に入れるもの
- 第2部 定年十年目でわかった、「第二の人生」を成功させる道しるべ
- 第3部 幸せな老年を生きるための、名医がすすめる具体策
この本の前半で、筆者は、「定年後を心豊かに生きる身支度 定年後で失うもの 手に入れるもの」について書いています。印象に残ったのは次のような点です。
- 失ったものを取り戻すことが至難であっても、それに替わるものを手にすることは、発想の転換と覚悟しだいではそれほど難しくない。定年退職で何を失ったかを明らかにして、それにどう対応するかを検討することで、これからの人生設計に役立つ豊富な情報が得られると思う。
- 私たちはこれまで肩書きに合わせて自分を膨らませてきたのである。自分でも膨らませすぎではないかと思っても膨らませ続けた「肩書きバブル」であった。それが、定年退職と同時に肩書きが取れて、ようやく余計なものを身に着けていない本来の自分に一歩近づいたと思えばいい。
- 定年退職後、職場由来のストレスがないことが一つのストレスになっていることもある。家で所在なく過ごしていることがストレスになっている人もいる。こういう人はとにかく何か仕事をした方がよい。これまでは仕事は向こうから勝手にやってきたが、これからは探して取りに行かなくては手に入らない。
- 職場中心のコミュニケーションはもう自分とは関係ないと考えて、まずは現在の立場で社会とのつながりを築く必要がある。町内会の行事、教養講座・趣味の講座での勉強、ボランティア活動への参加、スポーツジムなど、私たちのまわりにはコミュニケーションを広げられる場がいくつもある。
- 定年で失ったものがあまりに大きいために、関心の大半は失ったものへ向けられ、定年で手にしたものは関心の片隅に置き去りにされている感がある。しかし、定年で手にしたものを明確にすることがこれからの生活を充実させるうえで大きな力になるのは確かである。
- 現役のときは「忙中閑あり」で、「閑」がオアシス的存在だったが、今や「閑」が日常であり、たまの「忙」は元気の源になっている。定年後は、「閑中忙あり」が望ましいと思っているので、できるだけ「忙」を作り出す工夫をしている。
- 日々の生活の中で何か「やるべきこと」を確保することを考えなくてはならない。「やるべきこと」は仕事であっても、ボランティア活動であっても、勉強であっても、自分にとって「やるべきこと」だと思えることなら何でもいい。とにかく生活の足場を作るべきである。
- いくつになっても、また、どのような状況になっても、夢を持つことは必要だと思う。サラリーマンはこれまで仕事の中で夢を追い求めてきたが、定年後は残りの人生をエンジョイするための夢を見てはどうか。夢が夢で終わってもいい。夢を見ることが私たちの心を和ませてくれるのである。
- 定年退職した者は、現役ばりばりの人たちから見れば、もはやいてもいなくてもそう大して変わらない影の薄い存在なのである。そうと割り切ってしまえば、ことさら疎外感や孤独感にさいなまれることはないはずである。
この本の中盤で、筆者は、「定年十年目でわかった、「第二の人生」を成功させる道しるべ」について書いています。印象に残ったのは次のような点です。
- 働かなくても何とか食べていける人でも、働けるなら働いた方がいい。たとえわずかな収入でも、それがあることで心にゆとりが出てくる。そして、働いているという自覚が日々の生活に「張り」を与えてくる。
- 定年後も現役時代と変わらない知的レベルを維持しようと思ったら、かなりの努力が必要になる。仕事もしないで、ぼけっと日々を過ごしていると、それこそ知能の廃用症候群になる。廃用症候群とは、一言で言えば、「刀は使わないと錆びる」ということである。
- 定年退職した私たちが、久々にかつての仲間でまだ現役で働いている人にあっても、彼らは私たちが懐かしく思うほどには懐かしく思ってはいない。私たちは現役の人たちから見れば、存在感の薄い過去の人間であると思ったほうがいいのである。
- 「腐っても鯛」には、良いものは落ちぶれてもそれだけの価値があるという解釈とは、別の解釈もある。それは、外側から見て形が立派だからとして安心して買うと腐っていることもあるから用心しろというものだ。この「世間の目は厳しいぞ、謙虚になれ」という警告は、定年退職後の心得にもなっている。
この本の後半で、筆者は、「幸せな老年を生きるための、名医がすすめる具体策」について書いています。印象に残ったのは次のような点です。
- 生活習慣病や認知症の予防のために「一読、十笑、百吸、千字、万歩」を提唱している。これは一日に、①一度は新聞や本を読むこと、②十回は笑うこと、③百回を目安に何度かに分けて深呼吸をすること、④日記や手紙などで千字くらいは字を書くこと、⑤一万歩を目指してあるくことである。
- 欲望はエンドレスである。まだこの先に時間がたっぷりあると予想される若いころなら、欲望を追求することで発生する活力が生きる勢いの後押しになることもあるが、老齢期ではその活力が身を焼き尽くす炎にもなる。
- 健康によい食べ物を並べた語呂合わせとして「まごがやさしいよ」がある。「ま」:豆、「ご」:ゴマ、「は」:わかめ(海藻)、「や」:野菜、「さ」:魚、「し」:しいたけ(きのこ)、「い」:芋、「よ」:ヨーグルトを日ごろから食べるように推奨している。
- 現役のころには、やるべきことが四方八方から飛び込んできて、それをさばくのに大わらわだった。ところが現役を退いてからというものは、やるべきことが舞い込んでくることなどほとんど皆無になった。そこで私は自分でそれを探し出すか、作り出すことにしている。
- 年金だけで生活するのが苦しかったら、足らない分だけでも働いて稼げばいい。定年退職者にはそう簡単に仕事は見つからないだろうが、キャリアにこだわらず、見栄や外聞に蓋をして、給料が考えていたよりはるかに低くても、今の自分の評価額だと素直に受容できるなら、仕事は必ず見つかるはずである。
- 仕事のネットワークを介しての人脈は、仕事がなくなればつながりづらくなり、やがて途切れてしまう。だが、そこに仕事とは直接関係ない部分が少しでもあれば、その部分を介して人脈が通じることもありうる。
- 引きこもっていては新たな出会いはない。誰かが声をかけて誘ってくれるかもしれないと、じっと待っていても駄目である。よほど奇特な人でもない限り、声などかけてくれるはずがない、と思った方がいい。
- 「今日すべきことは明日には延ばさない」というこれまでの姿勢から、「明日できることは、今日はしない」方針に切り替えることにした。たったこれだけのことで肩の荷が大分軽くなったように感じられたから不思議である。ほどほどのいい加減さはたしかに気を楽にしてくれるものである。
- 定年後の夫は、妻にとっては「招かれざる客」であるくらいに厳しく認識しておいたほうがいい。定年退職したのは自分だけではなく妻も「サラリーマンの妻」としての役割を終えて、めでたく定年を迎えたという基本的な認識が大切だ。そして、双方で慰労と感謝の気持ちを伝えあうのが自然である。
- 夫婦は一心同体で、相手のことは何でも知っていると考えるのは思い上がりである。夫婦は双方が独立した人格を持ち、礼節と信頼と尊敬で結ばれた人間であり、そこにはむやみに踏み込んではならない領域があることを忘れてはならない。
- 定年後は時間がたっぷりあるとはいえ、無駄遣いしていいほど多くはない。定年後十年たった今、切実に実感していることは、「いつまでもあると思うな時と金」ということである。
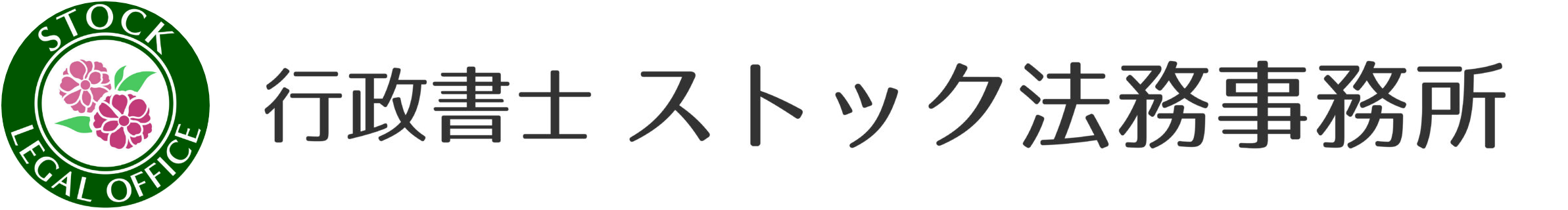
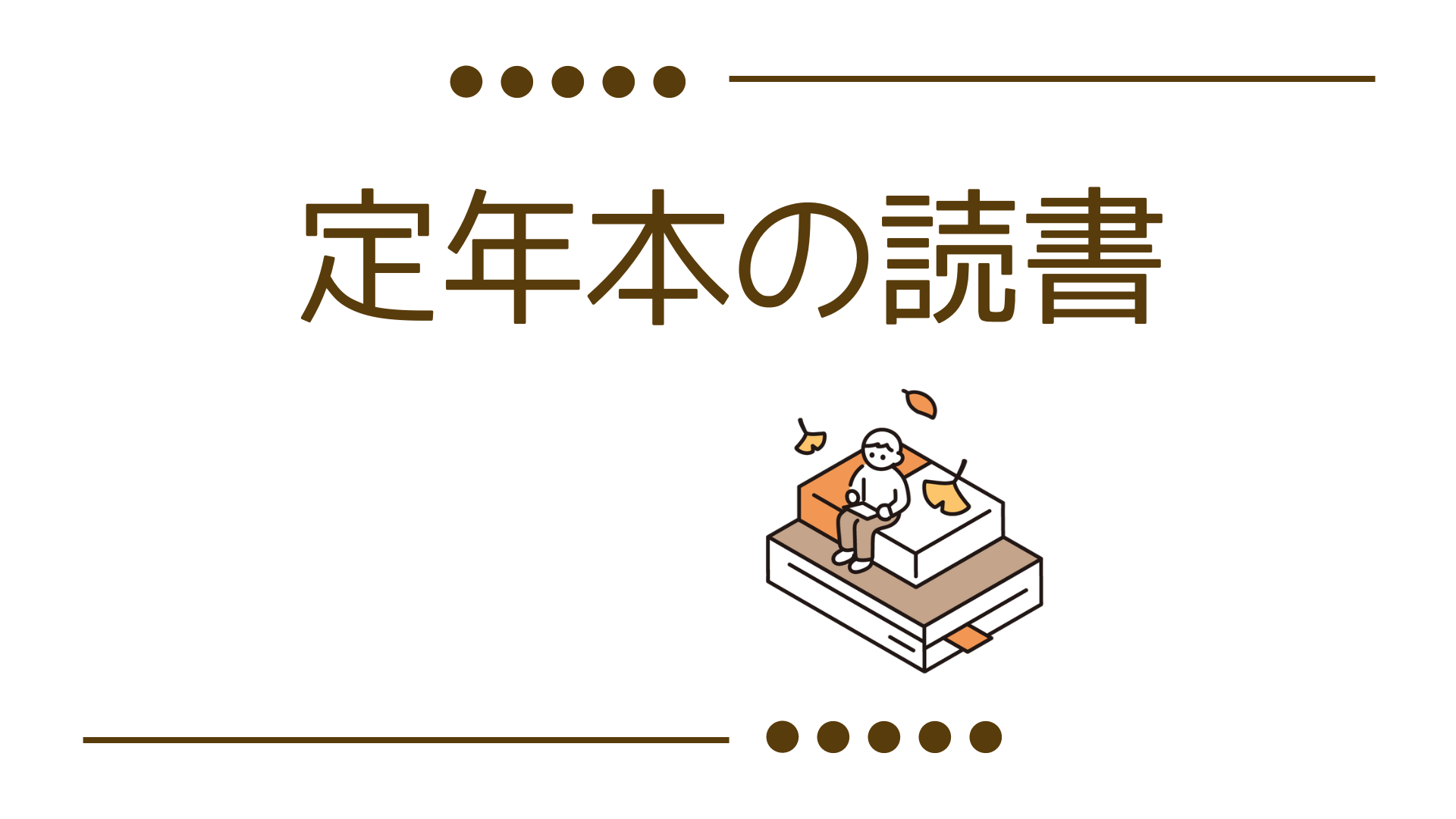
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3dd41da6.ebe4f3e8.3dd41da7.9a9a7bf0/?me_id=1249489&item_id=11435297&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcomicset%2Fcabinet%2F05018806%2Fbkbs9gbjulqdfpqg.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)