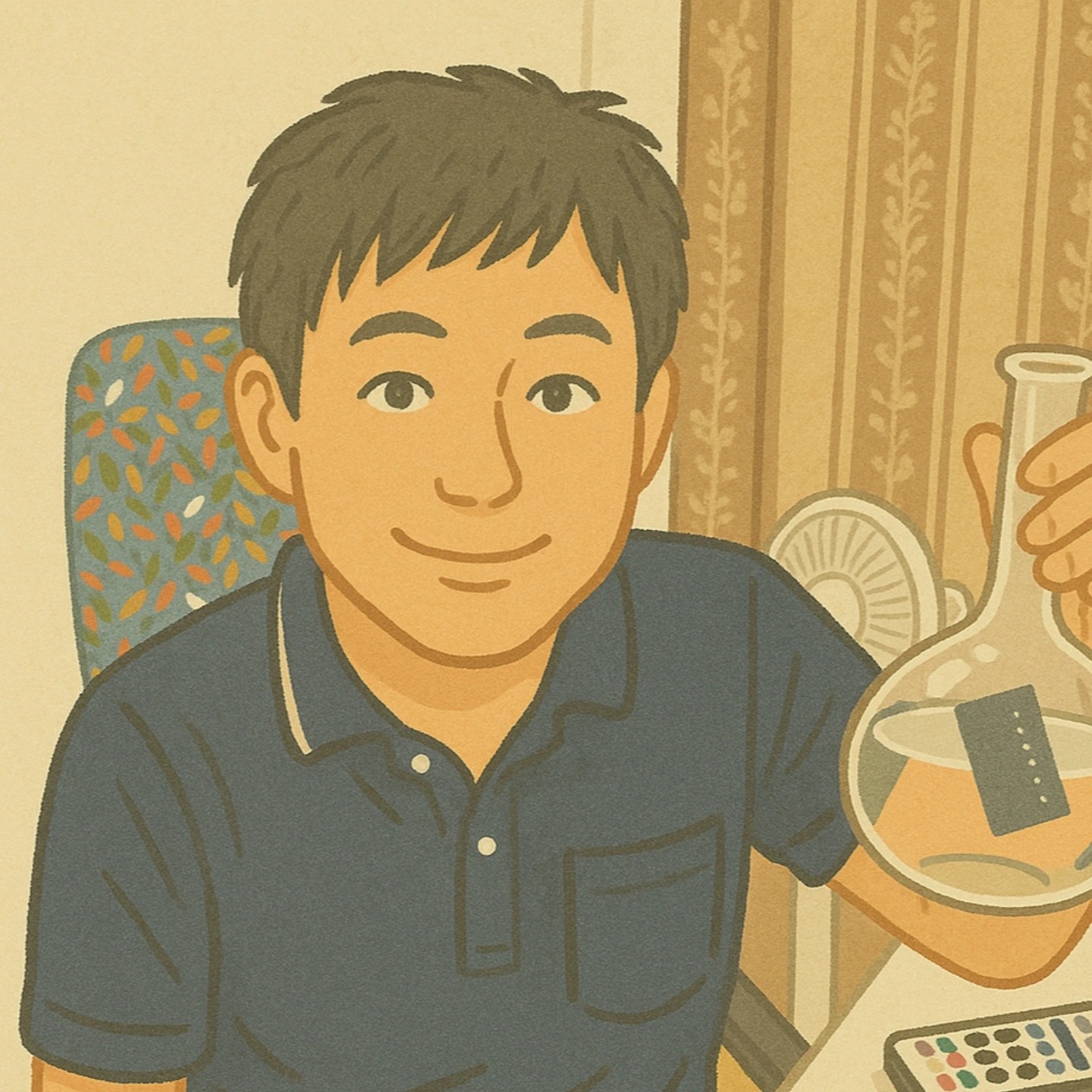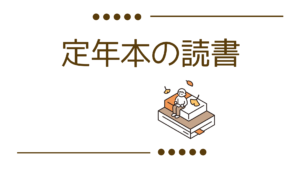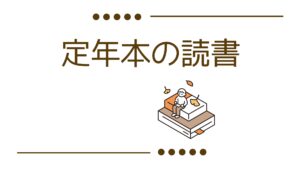この本では、「人生100年時代」における長い定年後の生き方として、日本人の旧来型の「新しい知識を注入し、知識の貯蔵量を増やす」勉強ではなく、「勉強しない勉強」を提案されています。この「勉強しない勉強」とは、これまでの人生で自分が蓄積してきた知識・経験などのリソースを最大限に生かすというというものです。そして、「リソースの活用とアウトプットを通じて実現される頭の鍛え方と使い方」こそが、「勉強しない勉強」の真髄であるとしています。老年期を迎える前の時期に、新しい勉強法を実践する生き方に発想転換し、後悔なく生ききってほしいと述べています。
筆者の和田秀樹さんは、東京大学医学部卒の精神科医であり、また、医療、教育などの評論家や映画監督などとしても幅広く活動されています。著書には「感情的にならない本」(ワイド新書)、「80歳の壁」(幻冬舎新書)、「大人のための勉強法」(PHP新書)、「この国の冷たさの正体」(朝日新書)、「人は「感情」から老化する」(祥伝社新書)など多数あります。
この本は、次の5章で構成されています。
- 第1章 新時代に知識依存型人間はもういらない
- 第2章 思考とアウトプットを重視する新しい勉強法
- 第3章 定年後を充実させる「思考」の極意
- 第4章 定年後を充実させる「アウトプット」の極意
- 第5章 前頭葉を意識しながら生きる習慣
この本の前半で、筆者は、「新時代に知識依存型人間はもういらない」「思考とアウトプットを重視する新しい勉強法」について書いています。印象に残ったのは次のような点です。
- 何よりもこれからの時代は、思考力の欠如した知識依存型の人間には生きづらくなるのは必至である。AI時代がさらに進めば、「物知り自慢の使い方知らず」の価値が暴落するのは、火を見るより明らかだからである。
- 単に知識量だけを誇っても所詮スマホにはかなわない。それを有効に使えなければ何の役にも立たない。知識は所有することに価値があると無意識に思い込んでいる場合や、知識の正しい使い方を知らない場合、やがては知識依存症候群のような状態に陥らないとも限らない。
- 最近の脳科学の世界では、中高年になったからと言って記憶力が悪くなるのではなく、記憶したことは脳に残っているが、それを記憶として呼び出す想起のはたらきが悪くなるという説がかなり有力視されている。
- 記憶の出力経路をしっかり意識してつくらなければ、知識注入型の勉強を重ねても、かえって記憶力まで悪くなっていく。
- 自説の正当性を信じて疑わない人は、新しい視点からの意見を受け入れることができない。自説とそれを支えてきた過去の学説が、あたかも宗教のような性格を帯びてしまう。
- 平成時代までの知識注入にばかり着目するような考え方の限界が来ているのではないかと思う。平成後のこれからは、「知識を材料とし、いかに思考を続けていくか」という視点、そして「その思考をいかにアウトプットするか」という視点が、非常に大きなカギとなると確信している。
- 定年後の世代がこれからの人生で何かをやろうとするときには、「楽しくやる」ことをいちばんの目標にするべきである。そのためにも、根性論や精神論ではなく、方法論を検討することがとても大切になってくる。
- 苦手なことをわざわざ選んで劣等感を持つより、得意なことを選んで、「自分は結構賢いな」と喜んで取り組める方がよっぽどいい。
- 得意不得意の分析とともに、自分がこれまで蓄積してきた知識や経験など、個人リソースを一度整理して見つめることをしてみてほしい。自分自身に関して気づかなかったこと、見過ごしていたことなどがあきらかになり、これからの方向性を定める手がかりになる。
- できない人は、要領よく課題をこなす人に対して、嫉妬したり卑屈になったりする傾向がある。そんなつまらない感情にとらわれて、時間だけ費やすくらいなら、できる人のやり方を真似してみることで、より良い方法論を入手するのが賢明の策である。
- 人は試行を繰り返すことで成功や成果にたどり着く。単に「失敗」だと言って、そこから次の試行へとステップアップできなければ、失敗地点にとどまるしかない。
- 情報に接して、知らなかった言葉や概念に遭遇したとき、意味を知らないまま曖昧にやり過ごすのではなく、とりあえずネット検索してみて、新しいニュースや情勢のポイントをその都度、把握することを習慣づけよう。ただし、知ったことをすべて記憶しなければならないという強迫観念は捨てる。
- 自分の成功要因、他者の成功要因を分析して自分の力にできる人は、確実に上達し賢くなれる。分析から学びえたものはもちろんのこと、分析過程における思考そのものが、ひとつの財産になる。
- 書斎にこもりきって自分だけの閉じた世界をつくり上げるのではなく、「もっと外に出よう」「もっと人に会って議論を重ねよう」「もっと多彩なアウトプットを楽しもう」という考え方が肝心である。ひとりっきりでコツコツ知識をため込むだけが勉強ではない。
この本の中盤で、筆者は、「定年後を充実させる「思考」の極意」について書いています。印象に残ったのは次のような点です。
- 大人が勉強をする究極の目的とは、世の中の自称、他人の言説に盲従するのではなく、自らの頭で思考する力を涵養することにある。また、思考を習慣にすることによって、脳の機能の低下を効果的に防ぐことができるという、ありがたい特典がある。
- いくら人生を長く生きてきても、思考することが習慣になっていない人は、矛盾も疑問も感じることができない。自由な発想も期待できない。思考力がなければ、変化がもたらす状況にその都度、柔軟に対応することは難しくなる。
- さまざまなことにツッコミを入れて、考えるきっかけにする習慣をつけていかないと、何を見ても聞いても、「データの裏付け」「説の根拠」「論理の妥当性」について疑問を抱かず、関心も湧かず、次第に脳は反応しなくなっていってしまう。当然、脳の老化は進行する。
- 問題を発見できなければ解決に向けての思考がスタートしない。問題発見能力によって、これまで誰もが見落としていたところにこそ、真の問題が存在していることに気づくことができる。それがその人独自の着眼点ということになる。
- 唯一不変の答えを求めるという姿勢は、結局、自らの思考の幅、思考の可能性をどこまでも狭めていくことにほかならない。そして行きつく先は思考停止である。
- 既存の知識に満足しているだけでは賢くなれない。実は自分が信じてきたこととは違う異論反論というものは、思考の幅を広げてくれるありがたい材料だということを知ってほしい。
- 確率の低いことを過度に恐れるようなまずい事態を回避するためには、思い込みや決めつけによって抱くイメージを、数字的データに照らし合わせて検証するという手順を踏む必要がある。
- 古びた自説の主義主張に近いものばかりに接していても、時代遅れの自分のこだわりを強化することしかできない。そうではなく、時代の変化に対するアンテナを磨き、「異論・反論・極論に多く接するという姿勢を大切にしてほしい。
- 自説を否定しない本ばかりに手を伸ばせば脳は老化する。自分にとって気分の良くない内容の本が思考を深めてくれる。
- 本を1冊完全読破しなければという固定観念があると、読むこと自体が大変なプレッシャーになってしまうし、集中力ももたない。そういう根性論で読書するのではなく、気軽につまみ食い感覚でいろいろな説に触れるというのは、かなりいい方法である。
- 「この本を読んでこう思った」とか「自分はこの本のこの部分とは違う考えだ」など、読後感を人に話すと、本の内容がしっかり脳に定着するというメリットがある。
- 思考をショートカットして、ある条件や特徴を備えたものに概念を当てはめるはたらきをスキーマという。スキーマは非常に便利であるが、これに頼りすぎると思考作業を阻害する要因となる。ものごとを非常に単純化して頭を使わなくなる。
- ものごとを〇×式に単純化する思考スタイルを二分割思考という。二分割思考のコチコチに硬直した思考ではなく、グレーゾーンを自由に行き来する、幅の広い柔らかな思考で脳の若さを維持してほしい。
この本の後半で、筆者は、「定年後を充実させる「アウトプット」の極意」「前頭葉を意識しながら生きる習慣」について書いています。印象に残ったのは次のような点です。
- 独学を捨て去るべき理由は、①知識の注入ばかりで活用しなければ、賢くなれないどころか脳の老化が進んでしまう、②人との直接的・間接的交流を積極的に図っていかなければ、間がもたず意欲もわかず、毎日を無為に過ごすヒマ老人への一途をたどるからである。
- アウトプット力は天性の素質ではない。アウトプットに対する苦手意識を取り払うには、リハーサルを惜しむべきではない。
- 人にものを伝える際、大切なのは、小説家が書く文章のように流麗であることではない。そうではなく、いかに相手が理解できるように言いたいことを自分の言葉で伝えられるか、その一点に尽きる。
- 誰かに話すというアウトプットを常に意識していると、「難解用語分かったつもりの意味知らず」というみっともない姿をさらさずにすむ。自己満足型の孤独な独学者との大きな違いは、アウトプットの実践を通じて、確実にコミュニケーション能力や表現力を磨いていけるという点である。
- アウトプットの場は、一方的な演説をするための場ではない。相手の存在を無視した思い込みや押しつけをしていることに気づかないという人は、相手のリアクションからしっかりと学んでほしい。
- 中高年男性の話が嫌がられるのは、相手が十分理解できていない様子だと、「こんなことも分からないのか」と相手を見下す点である。話自体がつまらなかったり、相手に分かりやすく話す能力がないという現実に気づいてない証拠である。
- 定年後は、もう現役時代のような競争はしなくていいのである。自分が勝っているとか優れているとかを常に気にしているようでは、豊かな人間関係は育めない。
- アウトプット的生き方を実践する際には、「人の話に耳を傾ける」ことを意識してほしい。そして、言下に人を批判しない、見下さないという基本的態度をしっかり身につけてほしい。
- 前頭葉が萎縮し始めれば、偶発的な状況に対応できず、柔軟にものを考えられなくなる。そして思考スタイルもマンネリ化していく。
- ルーティン化した日常こそが前頭葉の敵である。前頭葉にとって、予想と現実のギャップが大きければ大きいほど、それは格好の刺激になる。
- 加齢とともに思考や感情がワンパターン化しがちであるから、むしろ積極的に新しいものに触れ、新しい刺激を受けるようにしてほしい。多彩な状況を前頭葉に体験させることが、機能の維持・向上には不可欠である。
- 頭の中だけでシミュレーションして、どうせこんな結果だろうと片づけてしまうのではなく、自分の体を動かして、まずは何でも試してみる。これを「試行力」と呼んでいるが、とても刺激に満ちた行為である。予想の世界だけに生きるのではなく、ぜひ現実の世界で動いて試してほしい。
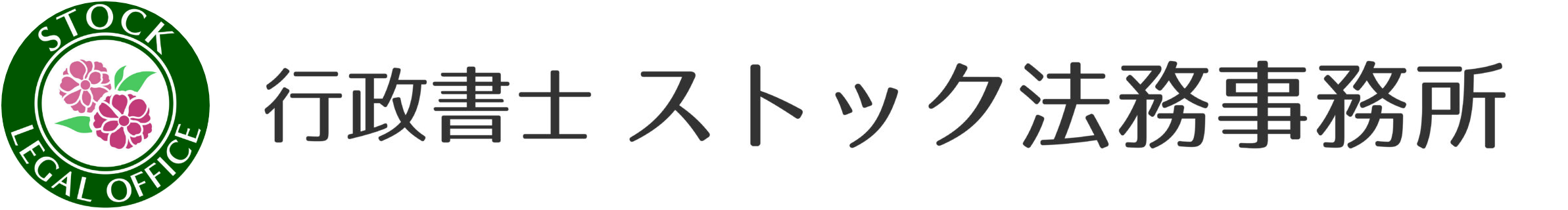
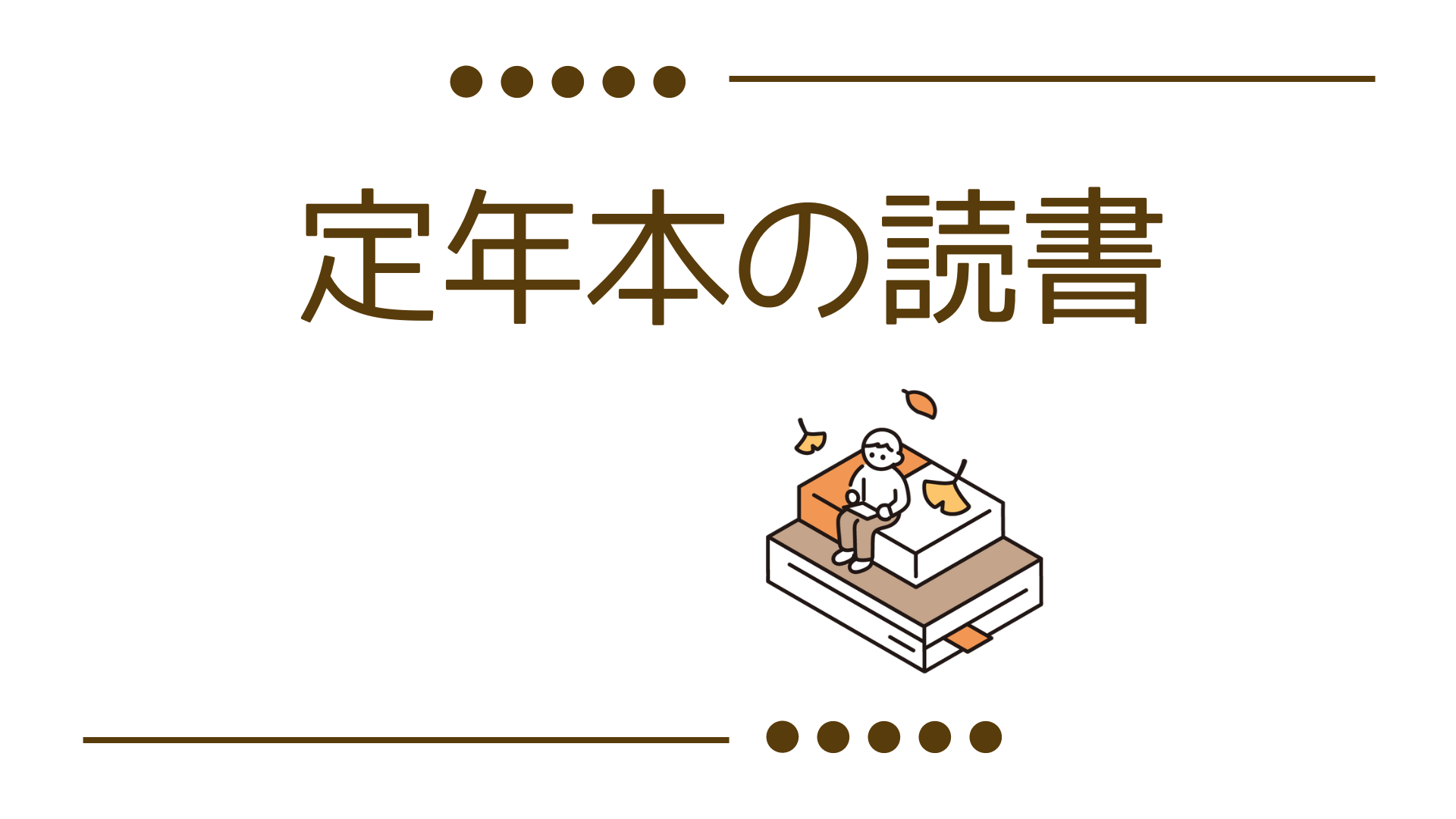
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/37c4e8aa.5274bab0.37c4e8ac.6b90fe35/?me_id=1213310&item_id=19327550&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9073%2F9784797399073.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)