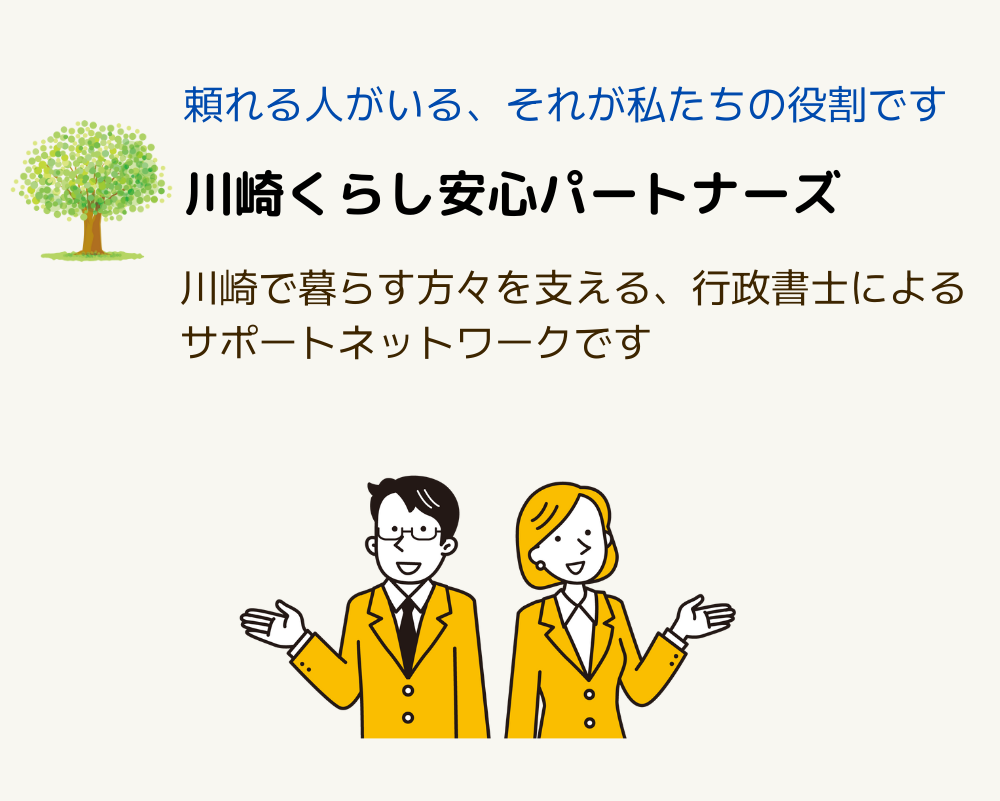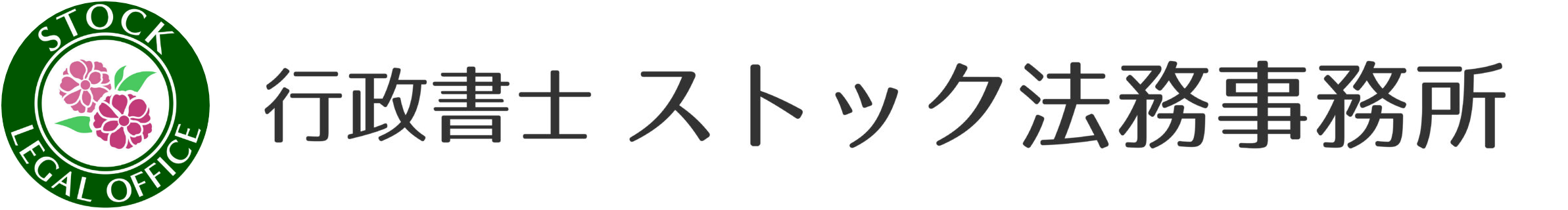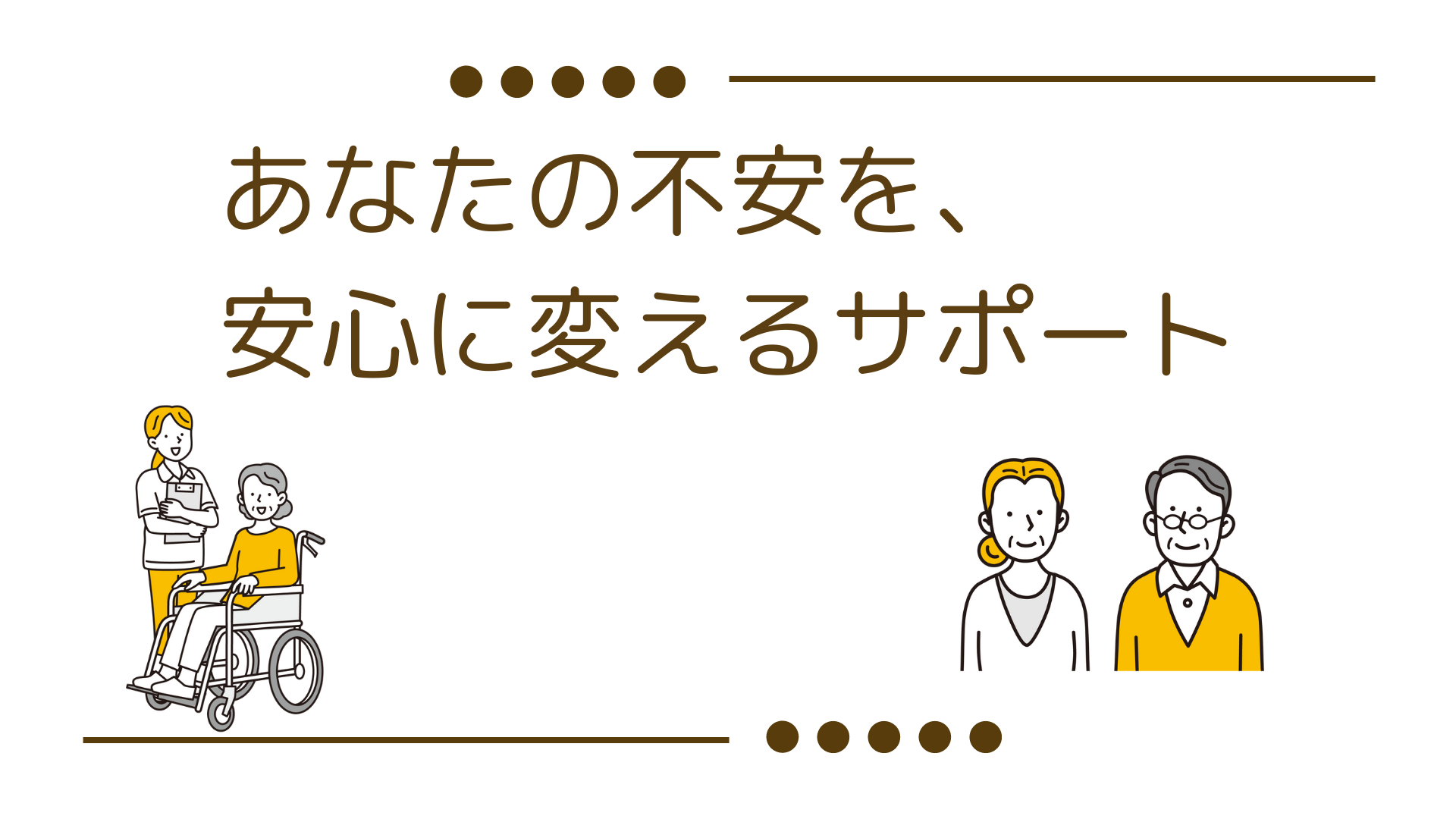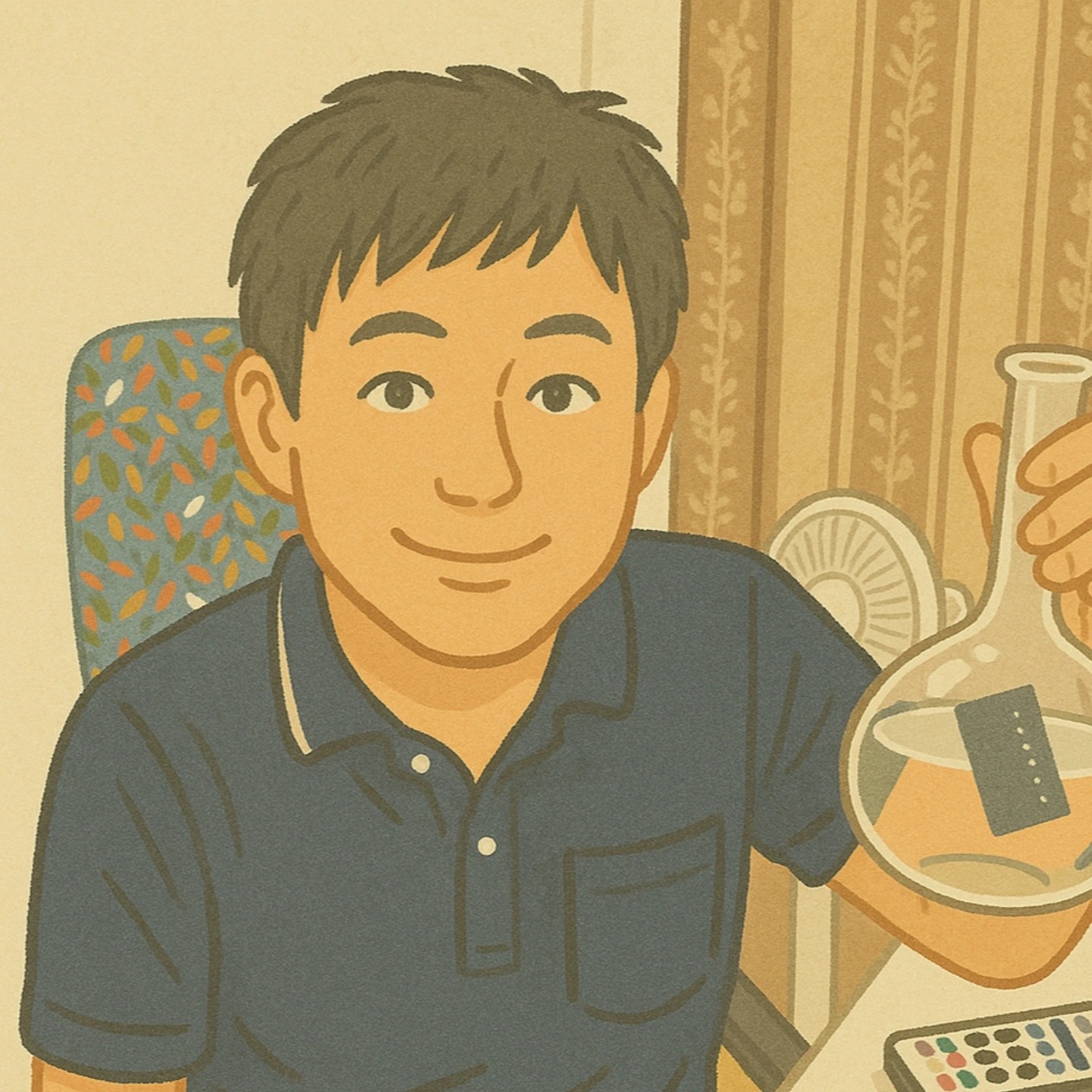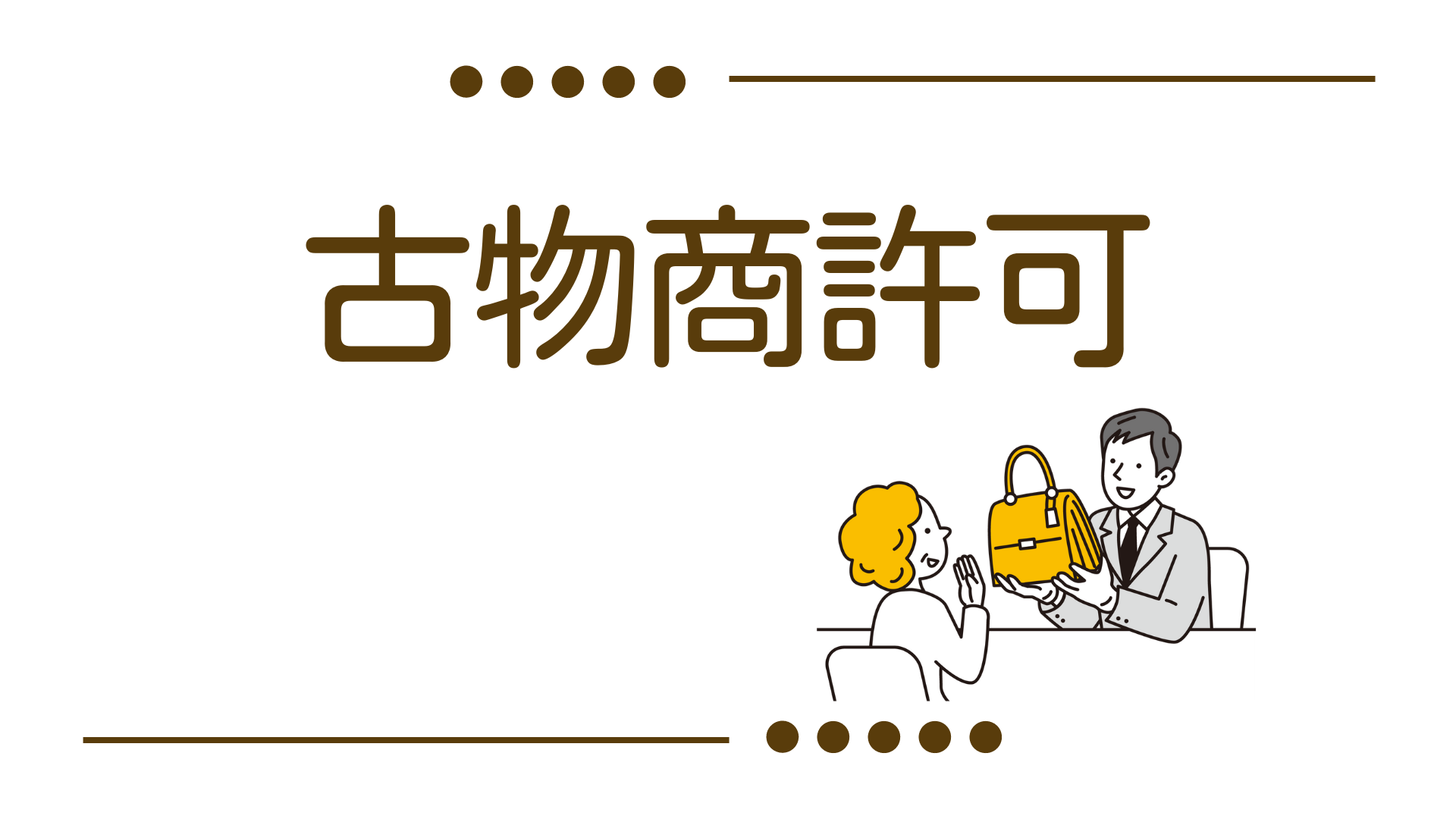高齢者施設や賃貸住宅への入居手続、あるいは病院での手続の場面で「保証人」という言葉を耳にすることがあります。
ただ、この「保証人」という言葉は、ときに誤解を招きやすいものです。特に「連帯保証人」という言葉と混同されやすく、「保証人を頼むと大きな金銭的責任を負わせてしまうのではないか」と心配する方も少なくありません。
実際には「身元保証人(身元引受人とも言われます)」と「連帯保証人」とでは役割も責任の重さも大きく異なります。ここでは、その違いを整理し、事前に理解しておくべき点をご紹介します。

身元保証人とは?
高齢者施設や病院では、多くの場合「身元保証人(または身元引受人)」を求められます。その役割は主に次のようなものです。
- 緊急時の連絡窓口になる
- 契約内容の確認や意思疎通のサポート
- 退所時の手続や引き取りの調整
- 入居費用や利用料が滞りなく支払われるよう、生活の安定を支援する
ここで大切なのは、身元保証人=必ずしも代わりに支払いをする人ではないという点です。
むしろ「滞納が生じないように、きちんと支払いが履行されることを保証する」立場と理解するとイメージしやすいでしょう。
例えば、法定後見人が財産管理を行っている場合は、その仕組みによって施設側が安心し、追加の保証を求められないケースもあります。

連帯保証人とは?
一方で「連帯保証人」とは、契約上の債務を本人と同じ責任で負う人を指します。
本人が支払えない場合には、基本的には施設や賃貸人へ請求でき、本人が支払い不能であるかどうかを確認する必要もありません。※契約内容などによって異なる場合があります。
つまり、本人とほぼ同等の支払義務を負う非常に重い責任が伴います。
高齢者施設においては、通常は「身元保証人」だけで十分なことが多いですが、中には「別途連帯保証人を立ててください」と条件を設けている施設もあります。
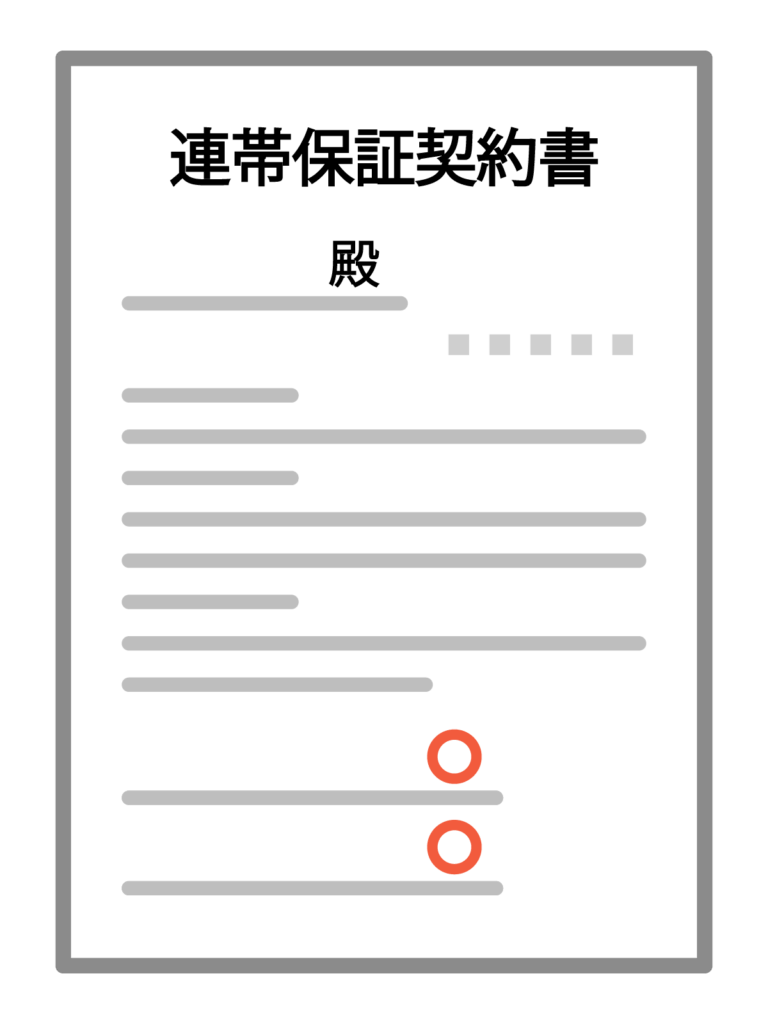
なぜ誤解が生じやすいのか?
「保証人」という言葉が使われると、多くの人は「連帯保証人のように支払義務を負う」とイメージしがちです。
そのため、本来は生活支援的な意味合いが強い「身元保証人」までもが敬遠され、身寄りのない高齢者の入居が難しくなる、という現実的な問題が起こっています。

事前に確認・準備しておきたいこと
契約条件をしっかり確認する
施設ごとに「身元保証人のみでよい」「連帯保証人も必要」と対応が異なります。専門家に契約書を確認してもらうのも安心です。
後見制度や任意代理契約の活用
将来的に判断が難しくなったときに備えて、財産管理や契約手続きを代理できる仕組みを整えておくと、施設側からも信頼されやすくなります。
緊急連絡先や必要書類を整理しておく
健康保険証や診断書、連絡先リストなどをまとめておくと、いざというときにスムーズです。
行政書士ができるサポート
行政書士は、こうした保証人や契約に関する不安を整理するお手伝いができます。
- 契約内容の確認やリスクの説明
- 任意代理契約・任意後見契約の作成支援
- 緊急連絡先リストや必要書類の準備サポート
特に「保証人を頼める家族や親族がいない」という方にとっては、事前に専門家へ相談することで、入居や生活に関する不安をぐっと軽減できます。
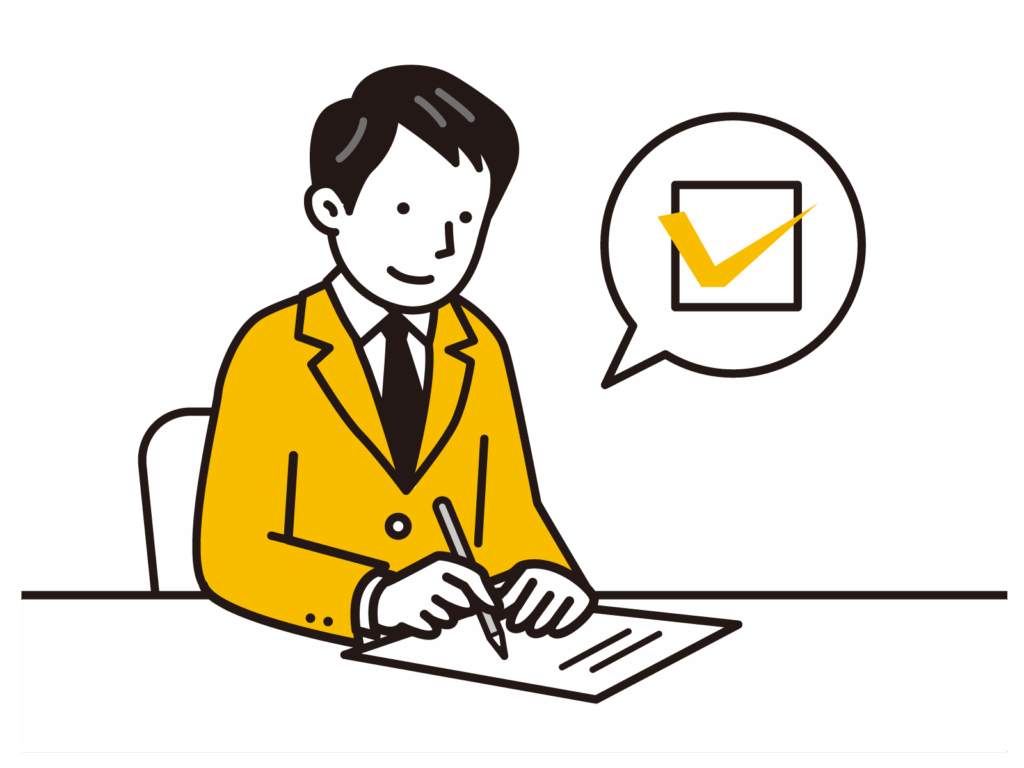
まとめ
- 「身元保証人(身元引受人)」は、主に生活上の支援や手続のサポートを担い、金銭的な支払い義務を直接負うものではありません。
- 「連帯保証人」は本人と同等の支払責任を負う立場であり、全く別の意味を持ちます。
- 契約によっては両方を求められる場合もあるため、事前の確認と準備が重要です。
言葉の違いを理解し、必要に応じて専門家に相談することで、ご本人もご家族も安心して生活を送ることができます。
行政書士ストック法務事務所は、川崎くらし安心パートナーズの一員として、あなたの不安を、安心に変えるサポートに取り組んでいます。